妊娠、授乳
妊娠しているときや、授乳中はお薬を飲んではいけないの?
| つわり治療薬サリドマイドを服用した結果、アザラシ症と呼ばれる短肢症の赤ちゃんが生まれて以来、妊娠と投薬の問題は大きくクローズアップされるようになりました。最近では、一般の方の間で妊娠中や授乳中はむやみに薬剤を服用しないようにという注意は、かなり徹底してきているようです。現在発売中の薬は全部動物実験を行い、胎児に影響があるか否か確かめられています。製薬会社はそのデータに基づき、理由および注意する期間や措置を定めています。ただし、ヒトで催奇形性の実験を行うことはできないので、動物実験の結果がヒトでもそのとおりとは言い切れず、厳密にいえば、胎児に対する安全性の確立された薬などはないといえます。 |
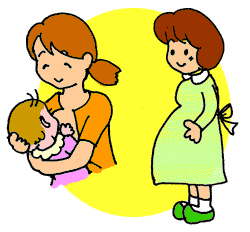 |
したがって、妊娠中や授乳中の患者さんは診察を受けるとき、そのことを忘れずに主治医に話してください。
しかし、薬剤による先天異常の発生は薬の種類によるばかりではなく、母体の体質や胎児の発育時期などほかの様々な因子によっても発生することが知られています。薬剤は必要性があって投与するものであり、安全だから投与するものではないという認識が必要です。
どうして?

<妊婦の場合>
母体について: 妊娠時には体のあらゆる代謝機能が亢進しているため、薬の効き方が変化して、有害作用へとつながる危険性があります。
胎児への影響: 母体に吸収された薬剤は、胎盤を通過し、さらに臍帯血管(へその緒)を介して胎児の体内へと移行します。そして、直接胎児の発育や機能に障害を与えたり、母体の臓器に変化を与えた結果、胎児にも何らかの障害を及ぼし、早・流産の原因となることがあります。
<授乳の場合>
内服した薬は消化管から吸収され血液中に入り、乳汁へ移行します。その量は一般に極めて少なく、有害ではないといわれていますが、乳児は1日500~1,000mlもの母乳を飲み、その解毒機構や排泄機構は大人ほど十分でないこと、また生後1週間以内の新生児では代謝に関与する酵素が欠損していたり、まだ能力が不十分だったりして薬物に対する感受性が大きいので注意しなくてはいけません。
添付文書の情報は変わることがあるの?
薬品添付文書の記載方法は、記載要領(平成9年4月25日「薬発第607号」)に従って記載されています。この要領では、A(データ)、B(理由)、C(注意対象期間)、D(措置)が定められており、A(データ)に対応するB(理由)が選ばれ、内容によってC(注意対象期間)、D(措置)が選択されます。D(措置)のうち、「投与しないこと」が「禁忌」に相当します。この記載要領は平成29年6月8日に改定されています(「薬生発0608 第1号」)。「妊婦」についての注意事項は、「投与しないこと」、「投与しないことが望ましい」又は「治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること」を基本として記載すること、とされています。「投与しないこと」は「禁忌」に相当します。また「授乳婦」についての注意事項は、「授乳を避けさせること」、「授乳しないことが望ましい」又は「治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること」を基本として記載すること、とされています。
妊婦は安全性の観点から薬の開発段階で臨床試験を行うことが困難なため、発売当初は動物実験の結果を根拠に、多くの薬が製薬会社の判断で禁忌とされています。発売から年月が経ち、臨床での使用経験などから妊婦に対する確かな情報が集まり、添付文書が改訂されることがあります。
厚生労働省は添付文書の改訂案を検討するためのワーキンググループを設置し、これまでの集積情報の整理・評価を行い、妊産婦・授乳婦への投与に関する情報の添付文書への反映に向けた事業を2016年度から開始しました。2018年、妊婦禁忌とされてきた免疫抑制剤「タクロリムス」「シクロスポリン」「アザチオプリン」の添付文書が改訂され、妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対し、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ禁忌が解除となりました。2022年にはCa拮抗薬2成分「アムロジピンベシル酸塩」、「ニフェジピン」が、2024年にはβ遮断薬「ビソプロロールフマル酸塩」、「ビソプロロール」、「カルベジロール」が解除されています。今後も対象は拡大する予定とされています。
このように添付文書の情報は変わることがあります。添付文書の情報だけで妊娠をあきらめたり、妊娠のために薬をやめてしまうことなく、まずは病院で相談してください。

