治療抵抗性統合失調症の治療
統合失調症治療の中心は半世紀前に発見されたドパミン受容体拮抗作用を持つ抗精神病薬で、統合失調症のドパミン機能異常仮説の根拠となっています。統合失調症の陽性症状(幻覚や妄想)に対し、約3割の患者さんでドパミン受容体拮抗薬(従来の抗精神病薬)は無効です。
クロザピン(商品名:クロザリル)は、2種類以上のクロザピン以外の抗精神病薬で十分な治療効果を得られない治療抵抗性統合失調症に対して有効であることが確立されている唯一の薬剤です。治療抵抗性統合失調症は、反応性不良統合失調症と耐用性不良統合失調症の2つに分けられます。
反応性不良統合失調症とは、忍容性に問題がない限り、2種類以上の十分量の抗精神病薬(クロルプロマジン換算600mg/日以上で、1種類以上の非定型抗精神病薬を含む)を適切な服薬コンプライアンスで十分な期間(4週間以上)服薬しても反応が認められなかった統合失調症と定義されています。ここで、反応の有無はGlobal Assessment of Functioning(GAF)という評価尺度を用いて評価します。
耐用性不良統合失調症とは、非定型抗精神病薬のうち、2種類以上による単剤治療を試みたが、(1)中等症以上の遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア、あるいはその他の遅発性錐体外路症状の出現、または悪化、または、(2)コントロール不良のパーキンソン症状、アカシジア、あるいは急性ジストニアの出現のために、十分に増量できず、十分な治療効果が得られなかった統合失調症と定義されています。これらの症状は、Drug-Induced Extrapyramidal Symptoms Scale(DIEPSS)という評価尺度を用いて評価します。
クロザピンは、治療抵抗性統合失調症に対し、有効性の基準によるものの、30%から60%に有効とされています。クロザピンは、難治性の陽性症状だけでなく、衝動性、自傷・他害にも有効で、治療継続率を上げ、入院期間を減少させます。一方、他の抗精神病薬よりも副作用に注意が必要で、重大な副作用((1)無顆粒球症好中球減少症、白血球減少症、(2)高血糖、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡、(3)心筋炎、心筋症、心膜炎、心のう液貯留)が起こる可能性もあります。そのため、クロザピン導入は血液内科医や糖尿病内科医との連携が円滑な入院環境で行われなければならず、用量の調整も非常に緩徐に増量していくことが定められています。しかし、治療抵抗性統合失調症と診断されてからクロザピン導入までの期間が短いほど、臨床効果が高い、という報告が複数あり、早期のクロザピンの開始が望まれます。
クロザピン専門外来
慶應義塾大学病院精神・神経科外来では、2016年10月より、毎週火曜日(午前)にクロザピン外来を開始することとなりました(担当医師 中島振一郎)。統合失調症の患者さんの中で、これまで服薬されてきたお薬の効果が十分ではない方、または、対応の難しい副作用のため、十分に服用ができなかった方に対して、クロザピンによる治療が適切かどうか、患者さん自身やご家族と一緒に医師が相談させていただき判断する外来です。
具体的には、治療歴・既往歴・家族歴の確認、評価尺度や検査を用いた統合失調症状の包括的な評価を行い、治療抵抗性統合失調症(反応性不良統合失調症または耐用性不良統合失調症)かどうかを判定します。また、身体状況の精査(歯科依頼、血液検査、心エコー、脳波、心電図、腹部X線)、クロザピンに対する禁忌の確認を行います。
クロザピンによる治療が適切とされた場合には、前の項で記しましたクロザピン治療によるリスクとベネフィットと入院による導入の方法について、文章と口頭にて丁寧に説明いたします。重症度、地理的条件、支援体制にもとづいて、当院またはクロザピン導入が可能な他院における治療の開始を検討いたします。受診希望の方は紹介状を準備の上、病院の初診予約センター![]() よりご予約ください。
よりご予約ください。
治療抵抗性統合失調症に関する臨床研究
統合失調症治療の中心は半世紀前に発見されたドパミン受容体拮抗作用を持つ抗精神病薬で、統合失調症のドパミン機能異常仮説の根拠となっています。しかし、統合失調症の陽性症状に対し、約3割の患者さんで従来の抗精神病薬は無効です。更に、最近の研究によりますと、治療反応性統合失調症ではドパミン生成能が亢進していますが、治療抵抗性統合失調症ではドパミン生成能の亢進を認めません。故に治療抵抗性統合失調症は従来のドパミン仮説では説明できません。
一方、グルタミン酸仮説は治療抵抗性統合失調症の病態を説明する仮説として有力です。グルタミン酸仮説は陰性症状(表出や意欲の低下)や認知機能障害も説明する可能性があり、ドパミン仮説より包括的な仮説とされています。近年、プロトン核磁気共鳴スペクトロスコピー(1H-MRS)という核磁気共鳴イメージング(MRI)技術の発展により脳内グルタミン酸を測定することが可能になりました。
1H-MRS研究によりますと、一貫して、初発統合失調症では線条体グルタミン酸濃度が高いことが報告されています。こうした背景から、グルタミン酸仮説に基づいた薬剤開発が現在進められています。しかし、統合失調症における抗精神病薬による治療反応性と線条体グルタミン酸の関係は不明です。更に、グルタミン酸は脳内ネットワーク結合性に不可欠な役割を担っていますが、統合失調症における抗精神病薬による治療反応/治療抵抗性の基盤となる脳内の構造的・機能的結合性とグルタミン酸の関係は不明です。
そこで、慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室では、マルチモーダルMRIを用いて治療抵抗性統合失調症の生物学的機序を解明することを目的に、臨床研究![]() を行っています(主任研究者 中島振一郎)。具体的には、年齢・性別・抗精神病薬をマッチした治療抵抗性統合失調症患者さん、治療反応性統合失調症患者さん、健常人における線条体グルタミン酸濃度や機能的・構造的結合性の測定と比較を行い、治療抵抗性の臨床症状・認知機能の神経基盤(機能的・構造的脳内結合性)におけるグルタミン酸の役割の解明を目指します。
を行っています(主任研究者 中島振一郎)。具体的には、年齢・性別・抗精神病薬をマッチした治療抵抗性統合失調症患者さん、治療反応性統合失調症患者さん、健常人における線条体グルタミン酸濃度や機能的・構造的結合性の測定と比較を行い、治療抵抗性の臨床症状・認知機能の神経基盤(機能的・構造的脳内結合性)におけるグルタミン酸の役割の解明を目指します。
本研究の意義は、治療抵抗性統合失調症についてグルタミン酸受容体介在型神経系の観点から新たな生物学的機序を発見し、統合失調症という疾患概念において、既存の薬剤に反応するドパミン系異常群と、治療抵抗性であるグルタミン酸系異常群を層別化し、グルタミン酸系神経機能の異常を焦点とした新たな治療法の開発に繋げていくことです。本研究が治療抵抗例に対するグルタミン酸系薬剤の開発に寄与し、そして、既存の薬剤が無効な症状からの回復と社会復帰を促進することを期待しております。
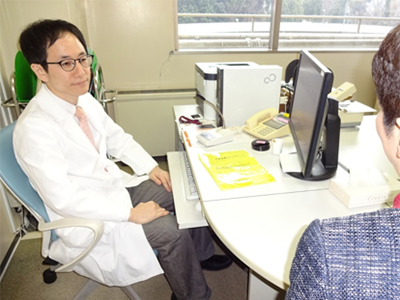
筆者
文責:精神・神経科![]()
執筆:中島振一郎
最終更新日:2017年4月1日
記事作成日:2017年4月1日